野球におけるリリーフの基礎知識
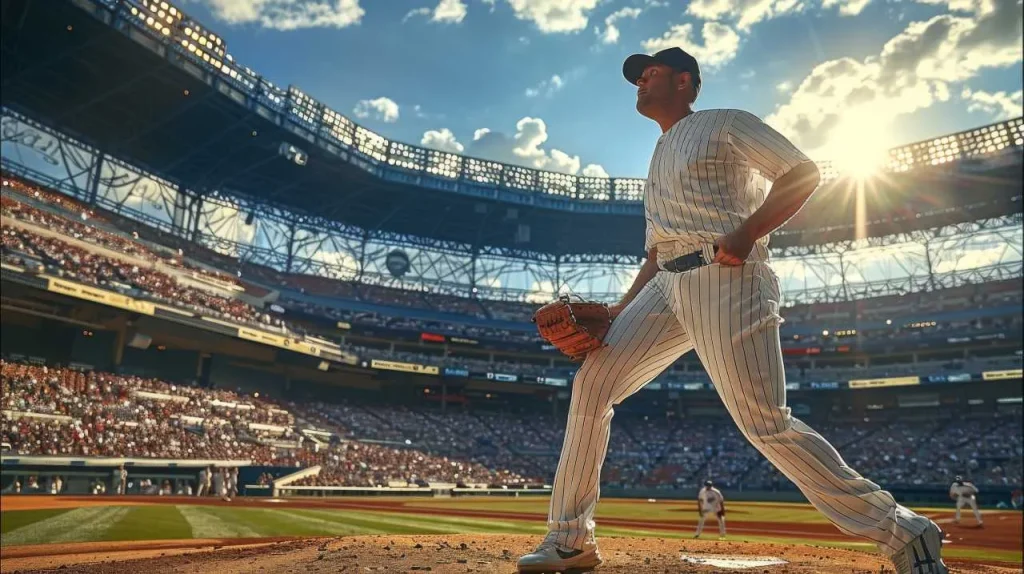
野球におけるリリーフについて、基礎知識をまとめました。試合における重要性とあわせて、わかりやすく解説します。
先発投手のあとに登板する投手のこと
リリーフとは、先発ピッチャー(投手)が降板したあとに登板するピッチャーを指します。relief(リリーフ)の意味は支援・援助で、日本語だと「救援投手」です。リリーフピッチャーが登板することを、「リリーフ」「救援」「継投」と言うことも。
少ない回(イニング)を投げるリリーフピッチャーは、複数の試合で連続登板するなど負担が多くなるため、チームは複数の信頼できる投手を揃える必要があります。
そのため、近年のプロ野球では役割分担を明確にし、強力な投手陣の構築を目指す、という意識のもとでリリーフピッチャーの育成と起用がされるようになりました。
リリーフが試合の行方を左右する
現在の野球では、リリーフピッチャーによる戦術の多様化が見られます。たとえば、バッター(打者)に対して相性のよいピッチャーを選択し、有利な状況を作り出す、なども戦術の一つ。
シーンに合わせたピッチャーの起用は、試合の流れを変えます。交代のタイミングや、どのピッチャーを登板させるかという判断が試合の勝敗を左右することも多いので、監督の采配に注目してみるとよいでしょう。
野球におけるリリーフの種類:抑え(クローザー)編

リリーフピッチャーは、大きく分けて抑えと中継ぎに分かれています。試合の最終盤に投げるピッチャーが抑えで、クローザーやストッパーとも呼ばれることも。抑えは、リードを維持したまま勝つことが主な役割です。
最終回で3点差以内のリードがある場面では、セーブがつく条件を満たすため、抑えが登板するケースが多い傾向があります。最終回は重要なイニングなので、大きなプレッシャーがかかる役割と言えるでしょう。
なお、日本プロ野球(NPB)では、リリーフピッチャーが最後までリードを守りきると、セーブと呼ばれる記録が残ります。セーブは、1974年にセ・パ両リーグで公式記録として導入されました。シーズンを通してもっともセーブ数が多いピッチャーは、最多セーブ投手のタイトルが与えられます。
野球におけるリリーフの種類:中継ぎ編

中継ぎ(ミドルリリーフピッチャー)とは、先発ピッチャーと抑えとの間に投球する選手のことです。中継ぎは以下のような種類に分かれます。
セットアッパー(抑えにつなぐ役割)
セットアッパーは抑えにつなぐ役割で、8回を投げるのが一般的です。リード時もしくは同点のときより確実に勝つために、登板します。
絶対に点をとられたくないシーンで起用されることが多いので、責任は重大。抑えと同等の力量のあるピッチャーが起用されます。プレッシャーがかかるので、メンタルの強さも必要です。
ロングリリーフ(先発が早期降板した場合の救援)
長いイニングを投げる中継ぎを、ロングリリーフといいます。登板するのは2〜3イニング以上が目安。主に、先発ピッチャーが大量失点やケガなどのトラブルで降板したときに起用されます。
ロングリリーフは、投げ続けるためのスタミナのある選手が多い傾向です。ちなみに先発ローテーション(複数の先発投手を登板させる順番)の登板間隔を調整するために長く救援することを、第二先発といいます。
ワンポイントリリーフ(特定打者に対応する投手)
バッター1人もしくは2人など、限定した相手・シーンに対応するために登板するのがワンポイントリリーフです。ショートリリーフやスポットリリーバーともいいます。
ワンポイントリリーフでは、特定のバッターに対して相性がよいピッチャーが選ぶ戦術がとられることも。ちなみに、左バッターを抑えるために登板するリリーフピッチャーを、左殺し・左キラーと呼ぶこともあります。
ただし、メジャーリーグ(MLB)では、時間短縮のためワンポイントリリーフが禁止になりました。3人のバッターと対戦するかイニングが終了するまで投げなければ、交代はできません。
敗戦処理(チームが大差で負けている場面で登板)
先発もしくはリリーフピッチャーが打たれ、大量リードを許したときに登板します。アメリカでは後始末をする清掃員(mop up man)から、モップアップマンとも呼ばれています。勝敗がほぼ決まった場面で、中継ぎ投手を温存するために、以下のようなピッチャーが登板するのが一般的。
- 中継ぎ投手よりやや実力が劣るピッチャー
- 登板経験を積ませたい若手ピッチャー
- 不調や怪我明け後の調整が必要なピッチャー
また、延長戦やタブルヘッダー(1日に複数の試合)などで投手を使い切った場合、野手が起用されることもあります。メジャーリーグでは、リードしているチームの野手は9回で10点差以上、リードされているチームの野手は8点差以上離れていなければ登板できません。
優秀なリリーフが選ばれる最優秀中継ぎ投手とは

最優秀中継ぎ投手とは、日本野球機構の投手タイトルの一つです。
ホールドポイント数(ホールド(リリーフピッチャーにおいて勝利への貢献度を評価する指標)+救援勝利の数を合計した数)が、多い選手が獲得します。
最優秀中継ぎ投手の歴代受賞者を、セ・リーグ(セントラル・リーグ)とパ・リーグ(パシフィック・リーグ)に分けてまとめました。
| セ・リーグ | パ・リーグ | |
|---|---|---|
| 2015年 | 福原忍(阪神タイガース) | 増田達至(西武ライオンズ) |
| 2016年 | S.マシソン(読売ジャイアンツ) | 宮西尚生(日本ハムファイターズ) |
| 2017年 | 桑原謙太朗(阪神タイガース) M.マテオ(阪神タイガース) | 岩嵜翔(ソフトバンクホークス) |
| 2018年 | 近藤一樹(ヤクルトスワローズ) | 宮西尚生(日本ハムファイターズ) |
| 2019年 | J.ロドリゲス(中日ドラゴンズ) | 宮西尚生(日本ハムファイターズ) |
| 2020年 | 清水昇(ヤクルトスワローズ) 祖父江大輔(中日ドラゴンズ) 福敬登(中日ドラゴンズ) | L.モイネロ(ソフトバンクホークス) |
| 2021年 | 清水昇(ヤクルトスワローズ) | 堀瑞輝(日本ハムファイターズ) |
| 2022年 | Y.ロドリゲス(中日ドラゴンズ)湯浅京己(阪神タイガース) | 平良海馬(西武ライオンズ) 水上由伸(西武ライオンズ) |
| 2023年 | 島内颯太郎(広島東洋カープ) | L.ペルドモ(千葉ロッテマリーンズ) |
| 2024年 | 松山晋也(中日ドラゴンズ) 桐敷拓馬(阪神タイガース) | 河野竜生(日本ハムファイターズ) |
| 2025年 | 大勢(読売ジャイアンツ) | 松本裕樹(ソフトバンクホークス) |
最優秀中継ぎ投手に注目しておくと、シーズンの優秀なリリーフピッチャーがわかるようになるはずです。試合の際には、その巧みなピッチングにぜひ注目してください。
野球のリリーフに関するよくある質問

野球におけるリリーフに関するよくある質問をまとめました。リリーフについての疑問を解消するために、ぜひ参考にしてください。
Q1. リリーフの人数は?
チームによってベンチ入り登録する人数は異なりますが、日本プロ野球だとリリーフピッチャーは6~8人です。メジャーリーグベースボール(以下MLB)では、10人ほどになります。
メジャーリーグのほうが登録人数が多いのは、シーズンあたりの試合数が160試合以上ありピッチャーに負担がかかりやすいから。原則として引き分けがなく、長時間の試合になりやすいことも理由としてあげられます。
Q2. 先発とリリーフの違いは?
先発とリリーフは、投球するタイミングが違います。
先発は初回から投球する投手のことを指し、リリーフは先発の次に投げるポジションすべてを指します。
そのほかにも先発とリリーフの違いを以下の表にまとめたので、参考にしてください。
| 先発 | リリーフ | |
| 登板の間隔 | 先発ローテーションに従い、中4日以上の間隔を空ける | 複数の試合を連続登板することが多い |
| イニング | 長いイニングを投げることが多い | 長いイニングを投げることは少ない |
| タイトル | 最多勝利投手賞最優秀防御率投手賞 | 最優秀中継ぎ投手 |
投球数制限や怪我のリスクを考慮して、試合ごとに異なるピッチャーを登板させるのが、先発の基本的な考え方です。1試合の投球数を減らせるため、肩や肘への負担を軽減できます。
Q3. パーフェクトリリーフって?
パーフェクトリリーフとは、リリーフ登板した投手が相手打者を1人も出塁させずに抑えることです。これに対し、先発から試合終了まで無安打無四死球で勝つことをパーフェクトゲーム(完全試合)といいます。
四死球や失策で出塁を許しても無安打無失点なら、ノーヒットノーランです。安打で出塁を許しても1人も生還させず得点を与えなかった場合は、完封になります。
Q4. 連続リリーフの最多記録は?
連続リリーフの最多記録を持つのは、北海道日本ハムの宮西尚生投手です。連続リリーフ登板の最多記録保持者は北海道日本ハムの宮西尚生投手で、2025年5月25日時点で882試合に達しています。
宮西尚生は、最優秀中継ぎ投手のタイトルを3回獲得。左投左打のサウスポーで、キレのあるストレートとスライダー、シンカーによってバッターを打ち取る優秀なピッチャーです。
リリーフの役割に注目しよう
リリーフピッチャーには、抑えや中継ぎなど種類があります。どのタイミングでどのリリーフピッチャーを選択するかは、重要な戦術の一つ。起用されるシーンやそれぞれの役割を理解しておくと、野球観戦をさらに楽しめるようになるでしょう。
ENSPORTS fanでは、野球観戦をたくさんの方々に楽しんでいただくために、観戦マナーや観戦初心者のためのルール解説記事なども公開中。そちらぜひチェックしてみてください。

















