野球のタイブレーク制の基礎知識

野球におけるタイブレーク制について解説します。
日本プロ野球で導入されている「12回制のルール」とあわせてチェックしておきましょう。
早期決着をつけるために導入された制度
タイブレークは延長戦におけるルールの一つで、9イニングなど規定の回数で決着がつかないときに実施されます。意味は「同一均衡を破る」で、早期決着をつけるための制度です。
点数が入りやすいように、ランナー(走者)が塁に出た状態からスタートします。
近年では、試合時間短縮を求める声が多いことから、タイブレーク制を導入するリーグや試合が増えてきました。ただし、国際的な共通ルールはなく、リーグや大会によって詳細は異なります。
日本プロ野球は12回制
日本プロ野球では、タイブレーク制ではなく12回制を導入しています。
12回を限度として、通常の試合と同じ条件で各チームが攻撃と守備を繰り返すのがルールです。12回で決着がつかない場合は引き分けになります。
日本シリーズの場合は、1回戦から7回戦まで12回制で開催しています。8回戦以降の試合は回数制限がなくなり、勝敗がつくまで戦うルールです。なお、日本プロ野球の2軍公式戦では、タイブレーク制が試験的に導入されています。
高校野球におけるタイブレーク制
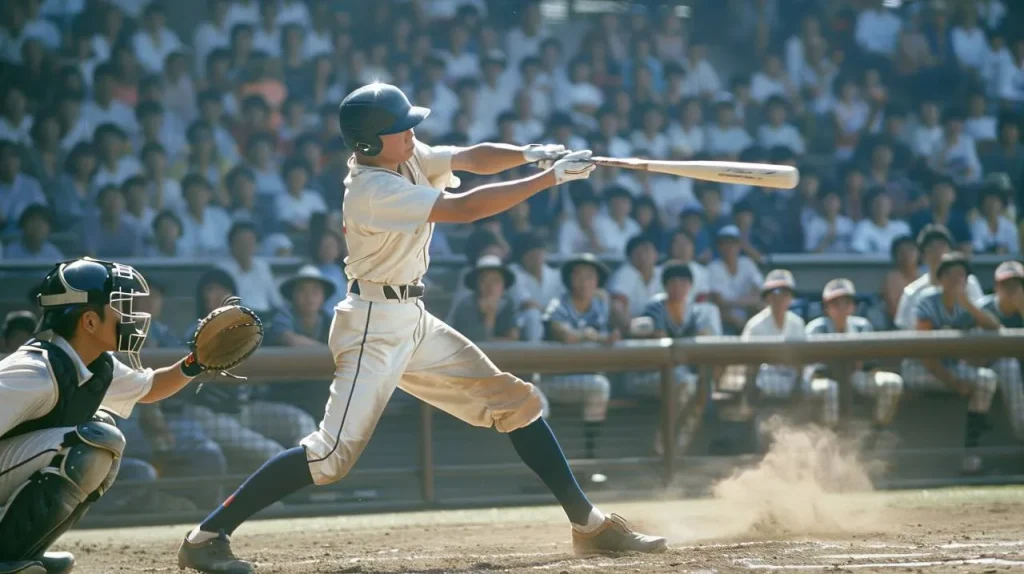
日本の高校野球の延長ルールは、タイブレーク制が導入されています。基本のルールと導入経緯について、わかりやすく解説するので基礎知識として知っておきましょう。
高校野球のタイブレーク制ルール
高校野球のルールは以下の通りです。
- 9イニング後の10回表から突入
- 攻撃チームはノーアウト一塁・二塁から始める
- 打順は前イニングの続きを継続する
- 一塁ランナーはイニング10回先頭打者の前の打順に名を連ねる選手
- 二塁ランナーは一塁ランナーの前の打順に名を連ねる選手
- 15イニング終了後も決着がつかない場合は試合を続行する
攻撃と守備を繰り返して、決着がつくまでタイブレークを継続するのが基本のルールです。ただし、1人の投手が登板できるイニング数は、15回以内までに制限されています。
高校野球でタイブレーク制が導入された経緯
高校野球でタイブレーク制が導入されたのは、2018年春の選抜大会から。当時は13回イニングからタイブレーク制に突入していましたが、2022年度からは10イニングからに変更されています。
目的としては、選手の健康を守るため、また運営を円滑化させるために導入されました。
そのほか、熱中症対策や、甲子園などの大会スケジュール調整をスムーズにすることも導入の理由としてあげられます。
MLBにおけるタイブレーク制

MLB(メジャーリーグベースボール)では、タイブレーク制が導入されています。基本のルールと導入の経緯をまとめました。
MLBのタイブレーク制ルール
MLBのタイブレーク制は、9イニング後の10回表から突入します。回数制限はありません。そのため、ノーアウト二塁の状態からスタートし、決着がつくまで勝負が継続します。
MLBでは野手登録された選手の登板は制限が設けられていますが、延長戦は例外です。野手が登板できるので、本職である投手の負担を軽減できます。
MLBでタイブレーク制が導入された経緯
MLBでは、2020年に感染症対策としてタイブレーク制を導入しました。その年は開幕が遅れ、公式戦が60試合に縮小されています。準備期間が短かった選手たちの負担軽減と、試合時間短縮による試合消化促進が導入の目的でした。
2023年には、タイブレーク制の恒久化を決定しています。以前から無制限の延長戦によるその後の戦い方への影響が懸念されていため、恒久化は自然な流れと言えるでしょう。
野球のタイブレーク制のメリット

タイブレーク制を導入するリーグや大会は増えています。導入するメリットについても、チェックしておきましょう。
試合時間を短縮できる
塁にでた状態からスタートするタイブレーク制は、12回制よりも試合時間を短縮できます。
野球は試合時間がとくに長いスポーツです。一部のファンからは、試合が長引くことを負担に感じる声があがっていました。高校野球やMLBでは延長戦が長引きにくいタイブレーク制が導入されており、ファンの負担軽減につながっています。
また、試合時間を短くする取り組みは他にもあり、NPBでは30秒ルール、MLBではピッチクロックや牽制ルールなどを取り入れています。
選手への負担を軽減できる
試合時間が長時間になることを防ぐことで、選手の負担を軽減できます。体力や集中力の消耗を最小限に抑えて、故障のリスクを防止します。選手層が薄いチームがいる高校野球では、ピッチャーの肩を保護することにもつながります。
緊迫の攻防が楽しめる
点が入りやすい状態から始まるタイブレーク制では、一つ一つのプレーが大きな意味を持ちます。予期せぬ逆転劇やサヨナラ勝ちなど、ドラマチックな展開にも期待できるはず。
タイブレークにおける緊迫の攻防は、野球観戦をより白熱したものへと変えてくれます。
野球のタイブレーク制のデメリット

メリットが多いタイブレーク制ですが、実は賛否両論がある制度です。タイブレーク制のデメリットについても解説します。
すぐに決着がつく可能性がある
得点が入りやすい状態からはじめるので、延長戦突入後にすぐ決着がつく可能性があります。
「自ら塁に出ていないランナーによって点が入ることがあるため、積み重ねがない」といった意見も。盗塁などのハラハラ感をじっくりと味わいたい場合は、あっけなく感じるかもしれません。
運要素が勝敗を左右する可能性がある
後攻チームは、先攻チームの得点を確認してから攻撃できます。後攻チームは追いつければ負けることはなく、先攻チームはサヨナラ負けのプレッシャーを感じることに。先攻と後攻はコイントスやじゃんけんで決めるため、運要素が強いといえます。
タイブレーク制が導入されている大会

タイブレーク制が導入されているリーグ・大会と基本のルールを、一覧でまとめました。
| リーグ・大会の種類 | タイミング | ルール |
|---|---|---|
| 少年野球 | 6回終了後 | ノーアウト一塁・二塁 |
| 中学野球 | 7回終了後 | 連盟・大会によっては導入 |
| 高校野球 | 9回終了後(一部7回) | ノーアウト一塁・二塁 |
| 社会人野球 | 9回終了後(一部7回) | 連盟・大会によっては導入 |
| MLB | 9回終了後 | ノーアウト二塁 |
| WBC | 9回終了後 | ノーアウト二塁 |
| オリンピック | 9回終了後 | ノーアウト一塁・二塁 |
タイブレークなど延長ルールは、年代によって変更されることがあります。上記の情報は2025年6月時点のものなので、試合観戦をする場合はくわしいルールをチェックしておきましょう。
野球のタイブレーク制に関するよくある質問

野球のタイブレーク制に関するよくある質問をまとめました。疑問を感じている方は、ぜひチェックしてください。
Q1. タイブレークの自責点はどうなるの?
A. タイブレーク開始時に塁にでているランナーがホームに帰った場合、投手の自責点にはなりません。ランナーの盗塁としても記録されないルールです。
自責点とは、投手自身の責任として記録される失点のことです。プロ野球では個人成績として記録に残ります。
Q2.タイブレークでは後攻が有利なのは本当?
A. 諸説ありますが、実際に「高校野球の甲子園では後攻が有利」といったデータがあります。
先攻チームの得点を見られる、先攻チームが得点すればプレッシャーをかけられるのが、後攻が有利だと考えられる理由です。
Q3.タイブレークに回数制限はある?
A. 大会やリーグによってルールは異なりますが、基本的にタイブレークには回数制限がありません。
決着がつくまで攻撃と守備を繰り返します。タイブレーク制でも長引くことがあり、2021年のパドレス対ドジャースでは延長16回を記録しました。
野球観戦ではタイブレークによる勝敗の行方に注目しよう
野球のタイブレーク制では、ランナーを塁に置いた状態からスタートします。試合の早期決着が期待できることから、タイブレーク制を導入するリーグや大会は増えています。
高校野球やMLBなどで導入されているので、基本のルールをチェックしておきましょう。一つ一つのプレーが勝敗の行方を左右する緊迫の攻防に、ぜひ注目してください。
ENSPORTS fanでは、野球観戦をたくさんの方々に楽しんでいただくために、観戦マナーや観戦初心者のためのルール解説記事なども公開中。そちらぜひチェックしてみてください。

















